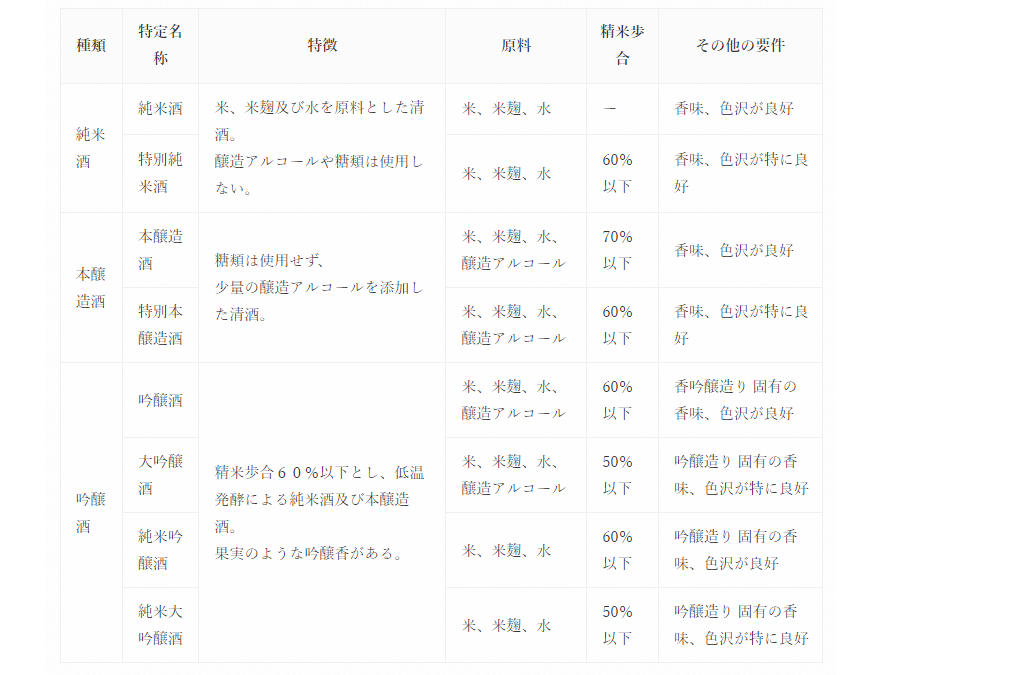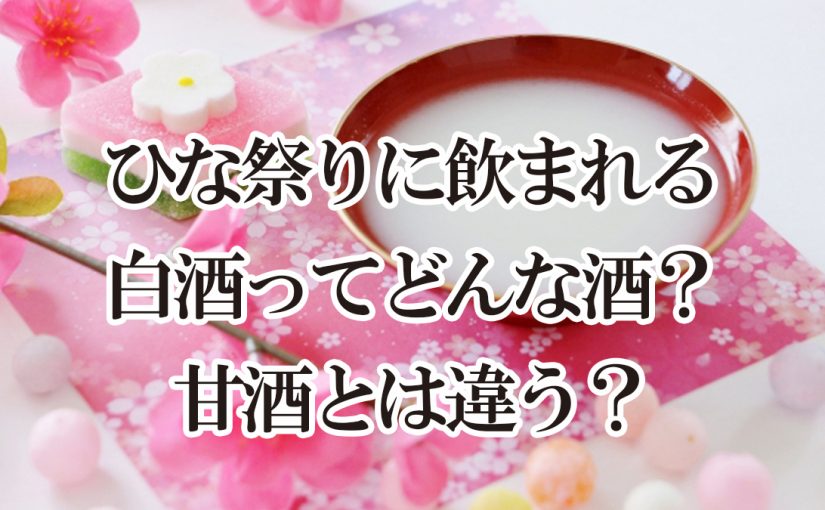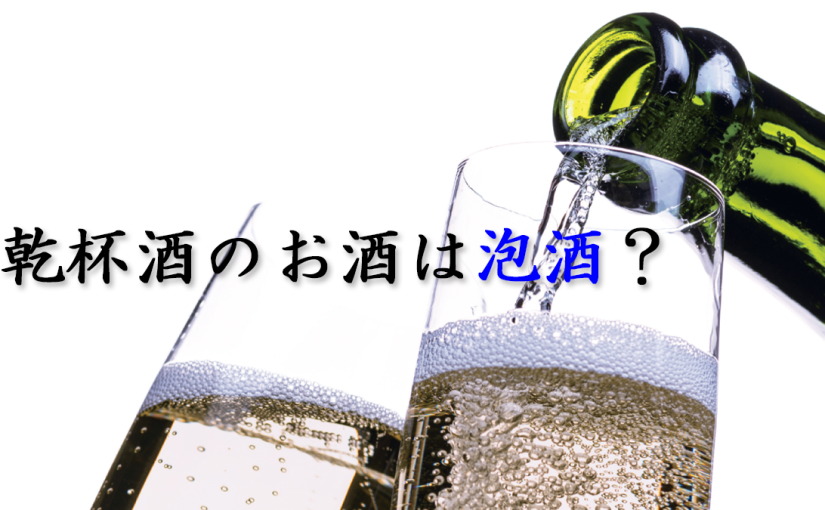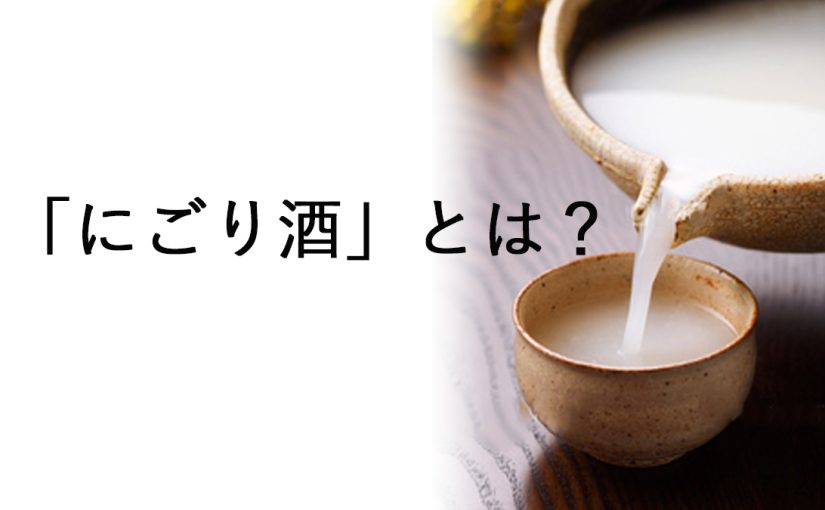開華蔵元が伝授する、簡単マメ知識
皆様、こんにちは! 日本名水百選の水が湧き出る栃木県佐野市で、延宝元年(1673 年)創業、 350 年以上の歴史を誇る栃木県内最古の蔵元、第一酒造の蔵人でございます。
私たちは、名水と自社栽培の酒米を用いて、やわらかな旨味と上品な香りの銘酒「開華」を醸しております。
今年も残すところわずかとなり、街は慌ただしさの中に一年の終わりを感じる時期となりました。日頃お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える日本の美しい習慣が「お歳暮」です。「いつ贈るのが正しいのか」「のしはどう書くのか」など、細かなマナーに戸惑われる方も少なくありません。
今回は、私たち蔵人が、「お歳暮」の歴史から、時期、相場、そしてお礼状に至るまで、感謝の心が伝わるための完全マニュアルを解説いたします。
1.「お歳暮」に込められた深い意味:ルーツは御魂祭にあり
「お歳暮」という習慣の起源は古く、二つの流れがあるとされています。一つは、江戸時代の商家や長屋での慣習で、盆と暮れの時期に、店子(たなこ)や商人が、大家さんや取引先へ「日頃の感謝とこれからもよろしく」という願いを込めて贈り物を届けたことに始まります。
そして、もう一つの根源は、年越しの準備として先祖の霊を迎える「御魂祭(みたままつ
り)」の名残とされています。当時、神棚や仏壇に供える塩蔵品や干物などの供え物を、親戚や近隣の人々に配る習慣があり、これが原型となりました。
現代のお歳暮にも、この「一年の節目に、大切な人の健康や、ご縁の継続を願う」という、温かい心が脈々と受け継がれているのです。
2.時期を逃さない心得:贈るタイミングと表書きマナー
お歳暮は、先方の年末の忙しい時期を避けるよう、少し早めに手配することが心遣いです。一般的に、お歳暮を贈る時期は 12 月初旬頃から、遅くとも 12 月 25 日くらいまでに届くように手配します。近年では、年末を避けて 11 月下旬から贈られる方も増えてきました。もともとは 12 月 13 日の「正月事始め」から贈るのが習わしでしたが、地域によって時期が異なる場合もありますので、先方の地域の習慣に合わせる心遣いも大切です。
もし手配が間に合わず、年内に届かなかった場合は、のし紙の「表書き」を変更するのがマナーです。年明けの松の内まで(一般的に 1 月 7 日まで)であれば、表書きを「お年賀」として贈ります。さらに時期がずれて、松の内以降、立春(2 月 4 日頃)を迎えるまでになってしまった場合は、表書きを「寒中御伺」または「寒中御見舞」と変えて贈るのが適切です。慌てて年内に間に合わせようとするよりも、時期がずれても適切な表書きを選ぶ方が、相手への敬意が伝わるものです。
3.感謝が伝わる金額と品選び:相場は相手への配慮
お歳暮は「お返し」を前提としない感謝の贈り物ですので、相手に気を遣わせないことが最も大切です。一般的な相場は、3,000 円から 5,000 円程度とされています。特別にお世話になった方へは 10,000 円程度の品を贈ることもありますが、高価すぎる品物はかえって相手に気を遣わせてしまうため、お互いに負担にならない程度のものを選ぶことが肝要です。
品物は、お正月など大人数が集まる機会に皆で消費できるものや、冬の味覚が人気を集めます。洋菓子や和菓子、ハム・肉類、そしてビールやジュースなどのドリンク類が、日持ちも良く定番です。私たち第一酒造の「開華」の日本酒も、名水で丁寧に仕込まれた柔らかな味わいが、年末年始の特別な時間を彩る品として大変ご好評をいただいております。お相手の家族構成や好みを考慮し、開けた時の笑顔を想像しながら選ぶのが、一番の心得です。
4.迷わないためののし紙マナー:水引と表書き
お歳暮ののし紙(掛紙)は、感謝の気持ちを伝えるための基本マナーです。
水引は、「何度あっても喜ばしいこと」に使われる、紅白 5 本の蝶結び(花結び)を使用
しますので、お歳暮に適しています。表書きは、前述の通り、贈る時期に合わせて「お歳暮」「お年賀」「寒中御見舞」などを記載し、今年限りの御礼として贈る場合は「御礼」とすることもあります。名入れ(水引の下部)には、贈り主の氏名をフルネームで記入するのが基本です。
文字の配置にも心得があります。表書きは、水引にかからないように、上から一文字分ほど空けて書き始めると、美しく整った印象になります。
5.感謝を確実に伝えるお礼状の書き方と例文
お歳暮を受け取ったら、贈ってくださった方に「無事届きました」という報告と、感謝の気持ちを伝えることが、最低限のマナーとなります。
お礼状は、お歳暮が届いたことを早く知らせるためにも、一両日中(遅くとも品物が届いてから 3 日以内)に投函するのがおすすめです。すぐに手書きのお礼状を書くことが難しい場合は、まず電話やメールで先に受領の連絡とお礼を伝え、その後改めて丁寧な手書きのお礼状を送付すると、より丁寧です。
お歳暮は、基本的に目上の方に、目下の方から感謝を込めて贈るものですので、お返しは基本的に不要とされています。しかし、お礼状は感謝を伝える上での最低限のマナーですので、必ず送りましょう。
(お礼状の基本例文:配送の場合)
拝啓
師走の候、寒さ厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、この度はご丁寧なお歳暮の品をお送りいただき、誠にありがとうございました。
早速、家族一同で(「開華の純米酒を」など、具体的な品名を入れるとさらに喜びが伝わります)
美味しくいただいております。
いつも変わらぬ温かいお心遣いに、心より感謝申し上げます。
寒さ厳しき折、皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。
略儀ながら書中をもちまして、お礼申し上げます。
敬具
令和七年十二月〇日
〇〇(ご自身の氏名)
〇〇様(相手の氏名)
お歳暮は、単に品物を贈るのではなく、一年間のご縁と感謝を再確認する美しい文化です。このコラムが、皆様の年の瀬のご挨拶の一助となれば幸いです。
私たち第一酒造も、皆様の「ありがとう」の気持ちにふさわしい、心豊かな味わいをこれからもお届けしてまいります。
どうぞ、良い年をお迎えください。
(第一酒造 蔵人一同)